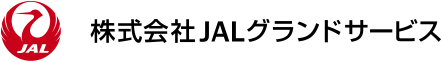客室
- - 快適な空の旅は整えられた座席から始まる -

清潔な機内を作り出す
チームプレー
フライトを終えた航空機は、休む間もなく次の目的地に向けて準備を始めます。給油や荷物の搭載など、地上でせわしなく準備が進む光景はよく見られますが、航空機の機内でも着々と用意が進んでいます。

客室スタッフの業務は機内の清掃と点検、備品を整えることが中心。お客さまがすべて降りた後の機内はピンと張りつめた空気が流れ、1チーム15名前後のスタッフが1分、1秒を惜しむように一斉に座席一つ一つを整えていきます。
シートまわりのゴミを片付け、ヘッドホンやブランケットなどの必要備品を用意し、機内誌を揃え、シートベルトを整え、テーブルを拭く……。これらの作業は役割を分担して行うチームプレーです。
一つ一つの作業を行いながら、さまざまなところに目を光らせ、指先を好感度センサーのように働かせています。小さなゴミはもちろん、機材の異常も見落とさないためです。

次のお客さまが快適に
空の旅を楽しむために
そしてもう一つ、客室スタッフにとって重要な仕事があります。それは機内放送の準備。フライト中にニュースを機内で放送するために、空港内のダビングルームで最新ニュースを録画し、各航空機に積み込みます。これも快適な空の旅をお届けするためのツールの一つです。
すべては、次に乗るお客さまが気持ちよく、くつろいで空の旅を楽しめるために……。それが客室スタッフの業務なのです。
スタッフ紹介

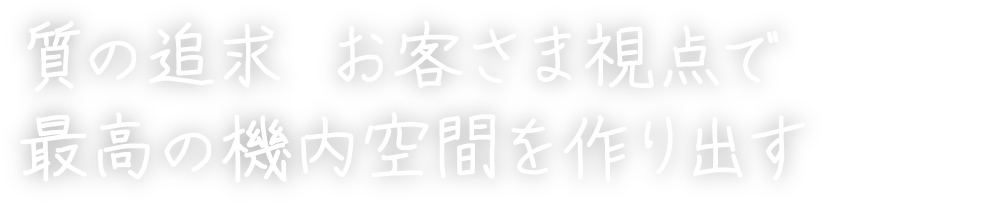
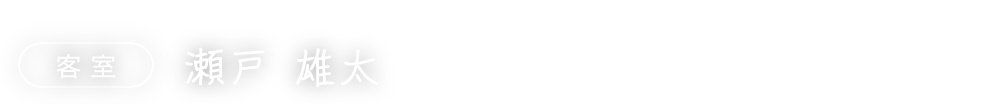
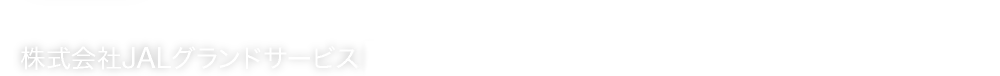
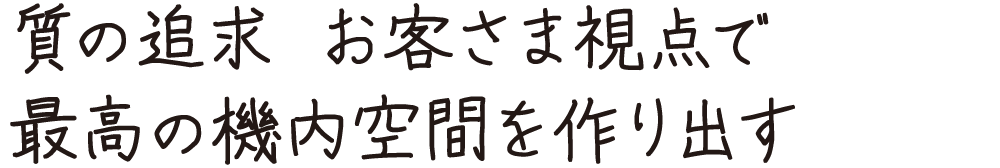
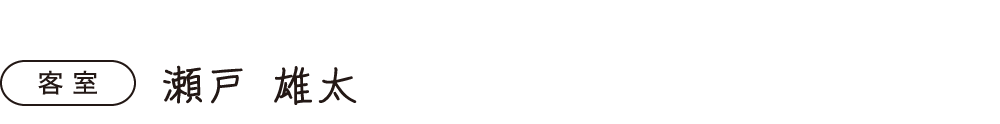
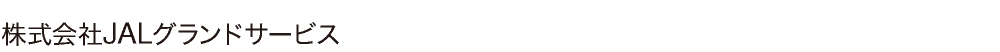

些細なミスも許さない
プロ意識
日本国内で1日の離発着数が最も多い羽田空港。とくに国内線では到着後、次の目的地への出発までの時間がごくわずか。着陸後の機内では、次のフライトに向けお客さまを迎え入れる準備が急ピッチで進められる。
「羽田空港の国内線は出発までの時間が短い便が多く、タイムププレッシャーを感じながらの仕事ですが、絶対にミスはできません。周囲の状況を的確に判断し臨機応変に動く必要があるため、常に自分を律しミスがないように気を付けています。」厳しい中にも常に笑顔を欠かさない瀬戸 雄太だ。
管理部門で仕事をする立場になった今も、頻繁に機内へ向かい、より効率的で確実な作業方法を考えている。どんな時でもプロ意識は欠かさない。

思い出に残る空の旅を
「初めての空の旅は小学生の時にJALで沖縄へ。航空機のカッコよさに惹かれ、お土産にモデルプレーンを買うほど航空機が好きになっていた。」と語る瀬戸。この旅行が航空業界を目指すきっかけとなり、今はこうして夢を叶えている。モデルプレーンは今も大切に飾っており、見るたびに初めての空の旅を思い出すという。
「航空機をご利用されるお客さまには思い出に残る空の旅をして頂きたいです。空の旅の中でお客さまと1番接点があるのは座席。客室乗務員がどれだけ良いサービスを提供しても、汚れがあると全てが台無しになります。お客さまに”JALが世界一”と思っていただける機内を提供し、自分のように、旅の思い出が『夢・憧れ』に繋がればさらに嬉しいですね。」瀬戸はそう語った。

一席一席にお客さまを想う
着陸後の機内に目を向けてみると、客室スタッフが次々に席を移りながら、流れるように作業をしている。シートベルトを整え、座席周りポケットの清掃・機内誌のチェック、そして同時に座面のゴミを床に落とす。ここまでの作業は、1席で約5秒程度。この作業と並行して、機内の床は別のスタッフが隅々まで掃除機をかけている。
「客室内はきれいなことが当たり前であり、私たちの仕事はその当たり前を確実に作りだす仕事です。一席、一席、座席を利用されるお客さまのことを想像して仕事をしています。そう思うと一切の手抜きはできません。」そう語る口調には強い決意が感じられた。

高品質な作業と
チームとしての一体感
「JGSグループの指差呼称をはじめとした各作業は他のエアラインと比べても非常に素晴らしい」
2020年より、JGSグループはIATA(国際航空運送協会)から地上作業に関する安全監査の認証(ISAGO認証)を取得している。
「私たちは直接お客さまと関わることは少ないですが、ターミナルや機内にいらっしゃるお客さまの姿が作業中によく見えます。それは、お客さまからも私たちの姿がよく見えているということです。高品質な作業をお客さまに見ていただくことで、安心・信頼をお届けできると考えています。そして、JGSグループ全社員が安全のプロフェッショナルとして基本に忠実に業務を遂行していることがISAGO認証の取得にもつながったと考えています。」
「JGSグループの良いところは、様々な人と一緒にチームとして仕事をするなかで、先輩・上司の垣根がなく一体感があるところ。」と瀬戸は語る。
今後はチームとしての一体感をより高め、世界一のグランドハンドリング会社を目指し精進していく。

自らの仕事で
JALファンを増やす
「自分が作業した便にお客さまが実際にご搭乗されているのを見たときに、自分の仕事が役に立っていると実感し、とてもやりがいを感じます。
また、客室乗務員や整備士などの多職種の仲間同士でもそれぞれの仕事に対し“ありがとう”と感謝の気持ちを積極的に伝えてくれることが多く、JALグループで仕事ができることに、誇りとやりがいを感じています。」
「今後の目標は、JALを選んでいただいたお客さまに、さすがJALだと感じていただける機内環境づくりに努め、JALファンを増やしていきたい。品質向上につながる部分はどんどん自分で変えていきたい。」そう瀬戸は語った。
将来的には海外での業務やJGSグループの良さを社内外に広く発信していく仕事にも携わりたいと言った。 瀬戸の目はJGSグループの明るい未来を見ているようだった。